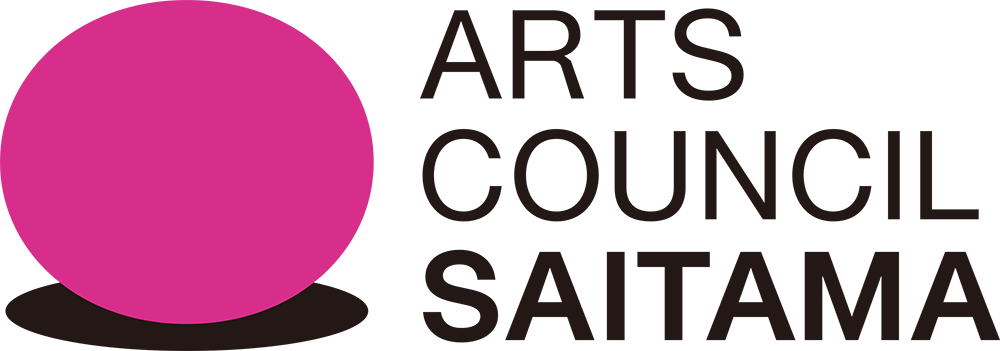プログラム
市民参加型アートプログラム
「さいたま ART ブリッジ 2025」

「さいたま ART ブリッジ 2025」は、市民が日常的にアートに触れ、新たな視点や創造的な喜びを体験するための参加型アートプログラムです。
場所や人との出会いを大切に、様々な市民がアートを通じてつながりを築き、豊かな地域社会を育むことを目指します。
パフォーマー、小説家やミュージシャンなど多様なアーティストを迎え、創作ワークショップや展示・発表を実施します。
-

市民参加型アートプログラム 【受付終了】「さいたま ART ブリッジ 2025」ベイビーシアター“Creation for baby”参加者募集!
- 令和7年度
-

市民参加型アートプログラム 【受付終了】「さいたま ART ブリッジ 2025」いしいしんじと絵本をつくろう!ワークショップ参加者募集!
- 終了
- 令和7年度
-

市民参加型アートプログラム 「さいたま ART ブリッジ 2025」廃品を使ってオリジナル楽器を作ろう!ワークショップ参加者募集!
- 終了
- 令和7年度
-

市民参加型アートプログラム 第6回 表現と場所の関係編
- 終了
- 令和6年度
-

市民参加型アートプログラム 第5回 身体とまちの関係編
- 終了
- 令和6年度
-

市民参加型アートプログラム 第4回 詩と公園の関係編
- 終了
- 令和6年度
-

市民参加型アートプログラム 第3回 アートと工場の関係編
- 終了
- 令和6年度
-

市民参加型アートプログラム 第2回 音と自然の関係編
- 終了
- 令和6年度
-

市民参加型アートプログラム 第1回 福祉の現場編
- 終了
- 令和6年度